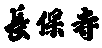長保寺多宝塔 1基 国宝
- 和歌山県海草郡下津町大字上 長保寺
- 明治三十七年八月二九日指定
- 昭和二十八年三月三十一日国宝指定
- 昭和二年解体修理
(財)和歌山県文化財センター 鳴海祥博
1998/10/25
長保寺は、和歌山県北部の海草郡下津町にある天台宗の寺院である。下津町は、北は藤代山系を境に海南市に接し、南は長峰山脈を境に有田郡と接している。西は紀伊水道に面した下津湾で、東は紀伊山脈に連なる山地となり、平野部はごく少ない。町のほぼ中央部の山中を南北に古代からの熊野参詣道が通っているが、北の藤白坂で紀ノ川流域の文化圏と区切られ、南は蕪坂で有田側流域の文化圏とも区切られ、一つの小天地となって、やや独自の文化圏を形成していたようである。
町内は、中央部を東から西に向かって延びる小さな山並みによって南北の二つの谷筋に分けられている。長保寺はその南側の谷筋の狭い平野部が深く山の谷間に入り込んだ辺り、熊野街道から海岸に至るほぼ中程に位置している。
伽藍は谷筋から流れ出る小さな宮川を境にその北側の緩い南斜面に営まれている。宮川を越えてすぐに大門があり、北に向かってなだらかな参道が延び、その両脇にはかつての子院跡と思われる区画が残る。参道の突き当たりの石段を登ると山腹を切り開いた敷地が開け、正面に本堂、右手前に多宝塔が建ち、左側には手前から鐘楼、阿弥陀堂、護摩堂が建つ。右手奥の一段高い位置には鎮守堂がある。参道正面の石段下を東に向かうと本坊である陽照院があり、東の山手の山中には紀州徳川家歴代藩主の広大な墓所が営まれている。 長保寺の創立は、寺蔵文書「長保寺記録抜書」(1)及び「慶徳山長保寺縁起并進状之写」(2)によると、長保二年(一〇〇〇)に一条天皇の勅願により創立され、寛仁元年(一〇一七)に伽藍の造営が終わったとされている。「縁起」は応永二四年(一四一七)の紀年を持つが、これらの文書はいずれも江戸期にまとめられたもので、その記述内容は両文書間で齟齬も見られ、にわかに信じがたいものとの指摘もあるが、今はこれ以外に徴すべき史料はない。
長保寺の名が史料に表れるのは、永仁六年(一二九八)の高野山文書「浜中南庄惣田数注進状写」(3)の中に「長保寺念仏免」とあるのが最も古い。「浜中南庄」は長保寺を含む地域にあった荘園で、この文書から「浜中南庄」は当時、高野山の金剛心院領であったことが分かる。
「浜中庄」は、寿永二年(一一八三)の仁和寺文書「摂政近衛基通御教書案」(4)に初出し、この文書を見ると近衛家が「高野金剛心院并浜仲庄」の本家職を、仁和寺が領家職を持っていたようである。高野金剛心院は、久安三年(一一四七)に摂政藤原忠実によって創立された高野山内の寺院で、近衛基通は忠実の曾孫に当たり、恐らく「浜中庄」は金剛心院の経営のために寄進されたものと推定でき、それ以前から摂関家領の荘園として成立していたものであろう。
長保寺のある浜中庄が、古い時期から荘園の領有を介して中央と関わりのあることは認められるが、この時期に長保寺が成立していたか、或いはこのことが長保寺の創立に関わっているのかどうかは明らかでない。
ところで、高野山文書「浜中南庄惣田数注進状写」の記述中には「長保寺念仏免」のほかに「同堂塔免」「千部経田」「仏性(餉)田」「湯屋免」があり、いずれも長保寺に関わる寺社免田と考えられ、当時の寺観の一端が窺える。このうち「念仏免」に関して、寺蔵文書に「不断念仏式」がある(5)。この文書は鎌倉後期のものとされ、それによると長保寺の不断念仏は大治三年(一一二八)に始まり、保元三年(一一五八)と正応二年(一二八九)の二度にわたって日数の改正を行い、少なくても延慶二年(一三〇九)まで継続していたことが分かる。先の「念仏免」は、この不断念仏式の経費に充てるためのものと判断できる。そしてこの文書の記述を信ずれば、長保寺の歴史は少なくても一二世紀前半までは遡ることができる。
次に寺蔵文書「長保寺記録抜書」の記述によれば、「仁治三年(一二四二)壬寅十月十五日釿初、十一月二十二日立斯、同二十六日上棟、但自西移干東改造之大工長命律賢等云云、」とあって仁治三年(一二四二)に寺地が西から東に移されたように解される。
また続いて「其後延慶四年(一三一一)辛亥被移上壇、釿初正月二九日壬寅卯時、礎同三月八日庚辰時、柱立同八日午時矣、」と記され、延慶四年(一三一一)には再度、本堂は「上壇」に移されており、これが現在の本堂の建つ少し高まった一郭を指すものと考えられ、本堂の建築年代も様式上この時のものと考えられている。
続いて正平十二年(一三五七)に現在の多宝塔が建立された(6)。
なお現在の大門を入ってすぐ左手にはかつての子院であった福蔵院があるが、江戸期以前この福蔵院は「大坊」と称されており、「上壇」に移る前の伽藍地の名残かもしれない。伽藍の移動は(7)、寺運の隆盛による規模の拡大を思わすが、一方で門前を流れる宮川の氾濫等自然災害がその契機となっているようにも思える。
次に寺蔵文書「慶徳山長保寺縁起并進状之写」に「雖*于大門頽破、蒙 後小松之院勅宣、為当寺之沙門*然願主、嘉慶二戊辰年課大工藤原有次」とあって、嘉慶二年(一三八八)に大門が再興され、これが現在のものと考えられている。寺院には「妙法院宮御筆 応永二四年(一四一七)六月一日」の刻銘のある寺号額が伝えられており、この時期の皇室との繋がりを物語っている。
その後の沿革はよるべき史料がなく明らかでないが、一七世紀に入って寛文七年(一六六七)に、紀州徳川家の初代頼宣が仏殿を建立し、それまでの高野山との関係を絶って天台宗に改めた(8)。寛文十一年(一六七一)に頼宣が没すると長保寺に埋葬され、墓所が営まれた。頼宣の建立した仏殿は陽照院と名付けられて長保寺の本坊とされた(9)。長保寺はその後、江戸期を通して紀州徳川家の菩提寺として藩の手厚い保護の下に護持され、歴代藩主の墓所が営まれた。
さて長保寺多宝塔についてみると、永仁六年(一二九八)の高野山文書「浜中南庄惣田数注進状写」の中に「同(長保寺)堂塔免」とあり、この時期には塔が存在していたと推量できる。現在の多宝塔の本尊金剛界大日如来像は十一世紀前半に遡るものとの見解も示されており、この像が客仏でない限り、長保寺には創立の早い時期には既に多宝塔が存在していたこととなり、このことは長保寺の創立縁起の真偽、或いは創立の経緯を考える上で大きな示唆を与えるものとなっている。
現在の多宝塔は心柱に「…正平十二年丁酉十月三日…」の墨書が有り、建立年次が明らかとなっている。
多宝塔の建立後の沿革は史料がなく明らかでない。建物を見ると、現在の外廻り内法長押の上の一段高い位置に長押の取り付いた痕跡があり、また内法長押によって隠れる位置の内法貫はすべて欅材で後世の取替材と見られ、何らかの大きな補修のあったことが窺われる。また軒廻りでは木負茅負と上重の飛檐隅木に当初材がなく、中古に軒廻りにかなり大きな修理があったように想像できるが、いずれも詳細は不明である。縁廻りもすべて後世の材に替わっている。それ以外の各部には古い材が残っており、かなりよく当初の姿を伝えているものと思われる。
昭和二年に解体修理が行われているが、現状変更は行われておらず、前述の外廻り内法長押の位置も復されていない。恐らく復原すると連子窓や板唐戸が再用できなくなるので現状修理の方針が採られたのではなかろうか。
多宝塔は本堂の右手前、境内の東南に南面して建つ。下重の平面は通例通り方三間で、中央に四天柱を立て、その背面通りには縦板張りの来迎壁を構え、前に禅宗様の須弥壇を置き本尊を祀る。
外部の間仕切りは、四面の中央間がいずれも、内部と外部の両方に幣軸を廻し、外側の幣軸に板唐戸を建て込む。内側の幣軸下端には付け樋端が残っており、また幣軸下方の寄せの上端には付け樋端の取り付け痕跡と建具の磨り減り痕跡があり、かつては内部に子持ち障子の立て込まれていたことが判る(10)。各面の両脇間は横板壁で、外部の腰長押と内法長押の間に連子窓を飾る。なお外部の内法長押は現在より一段高く取り付いていた痕跡があり、連子窓と板唐戸もかつてはその分せいの高いものであった(11)。
柱間寸法は、昭和修理時の実測図によると中央間が六・一一尺、脇間が四・五九尺で、総間は一五・二九尺となっている。支割は中央間が一六支で一支三・八一八寸、脇間は一二支で一支三・八二五寸となり、支割によって柱間寸法が決められているようである。ただ一支寸法がなにを基準に導き出されたのかは判然としない。
下重軸部は、四天柱と側柱では梁間方向にのみ足固め貫を通し、根太を受ける大引きとなっている。桁行き方向に貫は通さず、根太だけを配して固めている。側廻りでは更に腰貫と内法貫を通し、頭貫を落とし込む。腰貫はちょうど腰長押位置に入るが、貫下端は腰長押下端よりは少しこぼれて見えている。内部には腰長押がないが、腰貫の側面と壁板の面は同一面となっており、一見貫とは見えないような工作となっている。腰貫と内法貫はいずれも欅材で後補のものであるが、内法貫は隅柱位置で梁間材を上木に小根ほぞ差しとなっており、当初から入っていたと考えられる。
頭貫のせいは平が四・五寸、隅では五寸となっており、せいの増しの分だけ隅柱に延びが生じている。この隅延びの手法は本堂と同じであるが、本堂では頭貫先端が延びて木鼻となっているのに対し、多宝塔では頭貫は隅柱内で止まっており木鼻は出ない。
側柱には、外部に切目長押、重ね長押、腰長押、内法長押を打って固め、内部には内法長押だけを打つ。内法長押の取り付き高さは、現状では内外で異なっているが、前述の通り、柱には外部の内法長押が一段高く取り付いた痕跡と襟輪仕口が残っており、それを復すと内外とも同高となる。
四天柱は上方に天井長押を挟み込むように取り付けて固めている。四天柱の頂部には井桁に組んだ角材を載せ、その上に三斗組の組物を置いて下重の垂木掛けを組んでいる。この組物は天井裏で全く見え隠れとなるが丁寧に化粧に仕上げられている。
下重の地隅木上には井桁に柱盤を組み、その柱盤の四隅には更に火打ち状に梁を載せ、一二本の上重柱を立てている。桁行き方向の柱盤の中央位置には梁間に牛梁を架け、心柱を立てる。心柱の底部には長い丸ほぞを造りだし、牛梁を抜き通して納まっている。なお井桁に組んだ柱盤はほぼ同寸法の材が二段に重ねて置かれ、このうち下段のものはすべて昭和修理の際の取替材となっているが、修理前の図にも同様に描かれており、当初からの仕様であろうか。
上重の軸部の直径は六・四九尺で、下重軒の支割のちょうど十七支に相当しており、計画に当たって下重の支割寸法が基準となっているようである。上重の外部の間仕切りは、建物の規模が小さいからか、各間とも縦板を一枚張りとし、正背面と両側面の中央間だけは板の中央に定規縁状の材を打ち付け両開きの板唐戸に見せかけている。
上重柱は径六・三寸の丸柱で、見え隠れ部分も丸に仕上げている。上重柱のほぼ中程には貫が通る。この貫は正背面の柱には梁間方向に、両側面の中央間の柱には桁行き方向に同じ高さで井桁状に差し通され、また同じ位置で隅の柱のも通すが、この隅行きの貫は心柱があるため、心柱位置で切られて止まっている。またこの貫は上重柱から外方へ抜き出て縁の腰組組物を受けている。正背面と両側面の中央間の柱には、襷形に筋交いを打ち付けた欠き込みの痕跡が残っており、これが当初のものか否かは明らかでないが、同様な筋交いの痕跡は金剛三昧院の多宝塔にも見られ、案外古い時代から筋交いによる補強の考えがあった様にも思える。
上重の軸組は外部から見ると、内法長押を打ち、頭貫を入れ、柱上に台輪を納める、通常の形式に見える。しかし内部を見ると、柱上に断面矩形の大きな材が三段に重ねられている。つまり柱は内法長押から上方が外側半分だけの半柱となり、内法長押に見える材は実際は台輪状の角材で、半柱部分を抜き通して納められている。その上に頭貫に相当する角材が重ねられ、台輪がほぞ差しに納まっており、上重軸組を固めるための工法にかなりの工夫と考慮が払われている。
上重の柱、長押、頭貫、台輪はいずれも楠材を用いている。
下重の組物は出組で、実肘木を置いて丸桁を受ける。柱通りの通り肘木から丸桁にかけては軒支輪を架ける。柱通りの通り肘木と一手先目の秤肘木に直交して納まる手先方向の繋ぎ肘木は内部に長く延び、四天柱にほぞ差し鼻栓止めとなっている。
三つ斗の真々寸法は一・五三尺ほどでちょうど四支分となっており、また巻斗幅は五・六寸で一支と垂木幅にほぼ等しく、六支掛けとなっている。隅行きの肘木は幅が三・二五寸で平の二・七寸の一・二倍である。隅行き肘木とその先端に載るは鬼斗は一材から造り出され、隅の強化が計られている。なお下重の組物は大斗と方斗それに隅行き肘木が楠材、その他は檜材で、使用部位で材質の使い分けが意識されている。
中備えは各間とも蟇股で、脚内は繊細な薄肉彫りの彫刻となり、この彫刻部分は脚と一材から彫り出されている。彫刻の文様は、各面の三間がそれぞれ同一のもので、各面ごとにその文様を異にしている。正面と西側面は蓮華文、背面は笹竜胆文を中心飾りに置いた均整のとれた華やかな左右対称形文様であるが、東側面は参詣の動線から遠いからか、竹を表現しているらしいやや簡素な左右非対称形の文様となっている。これらの蟇股はすべて当初のものと見られるが、脚の輪郭の繰り型曲線は、本堂の向拝の蟇股曲線とは明らかに異なっており、工匠の系統の差を示しているように思われる。
上重の組物は多宝塔の定石に従い尾垂木付きの四手先組物で、実肘木を置いて丸桁を受ける。壁付きの組物は三つ斗を二段に積み重ねる形式となっているが、この壁付きの組物は外部だけの見せかけで、実は見え隠れの内部では角材が積み重ねられた状況となっている。一段目と三段目の枠肘木は、内部は通り肘木状に一材で通されており、外部だけが枠肘木形に造り出されている。一段目巻斗と二段目通り肘木、三段目巻斗と四段目通り肘木、四段目巻斗と五段目通り肘木は、いずれも断面矩形の一材から巻斗と肘木と面戸部分が造り出されている。
手先の肘木は柱位置から丸桁にかけて放射状に出るが、その割付は、丸桁の前面或いは巻斗の前面辺りを基準としているらしい。丸桁の組手真々間に丸桁鼻を手挟んで二五支に垂木を配し、それを五支ずつに等分して手先肘木を割り付けている。丸桁位置での三つ斗と垂木の関係は、実肘木下の三つ斗の外々寸法が一・五五尺に対して、垂木三支と垂木幅一つ分の寸法が一・五二五尺で、「四支掛け」とでも言えるような取り合わせとなっているが、果たしてどの程度計画性が意識されたものかは明らかでない。
丸桁の真々距離は一一・一四尺で、これに対し上重の塔身の直径は六・四九尺であり、塔身の通り真から丸桁の出は二・三二五尺となる。これを四手で持ち出し、塔身の通り真から三手先の通り肘木までは一・七七五尺、三手先目から四手先目までは五・五寸となっている。
手先の肘木と巻斗は、丸桁下の秤肘木と巻斗、実肘木も含め、それぞれの放射角度に応じて菱形に造られている。ただし大斗は各柱位置とも矩形で、円形の台輪に合わせて配置しており、手先の放射角度に対する変形はない。大斗の幅は平が六寸で、隅は六・五寸と少し大きくするが、三本の手先肘木が出る隅位置では、やや大斗が小さすぎる感じが否めない。
隅行きの肘木は幅が 寸で平の肘木幅 寸に対し 倍程になっている。各段の隅行き肘木はその上の巻斗や鬼斗と面戸部分までが一材から造り出されており、実体は角材を隙間なく積み重ねたものとなっており、構造の強化が計られている。
上重の組物は、秤肘木と実肘木と支輪受けの通り肘木が檜材で、その他は手先肘木の一部に檜材が用いられている以外は楠材を用いている。実肘木と丸桁は一材から造り出されていた。
組物の上方には軒小天井が張られるが、小天井の割付は、柱通りの天井桁から三手先目の天井桁の間を五等分するものとなっており、垂木の支割より細かくなっている。軒支輪の割付はこの軒小天井の割付に合わせている。
下重の軒は二軒の繁垂木で、配付垂木は地軒が七本、飛檐軒は論治垂木を含め五本である。軒の納まりについては精査できないが、修理時の実測図や現状を見ると、垂木の支割寸法は柱間部分と地垂木の配付け部分は、一支寸法が三・八二二五寸となっている。論治垂木も定石通りに納まるが、飛檐垂木の配付け部分の支割は一支が と少し広くなっている。茅負と木負は近世及び昭和の材となっているが、垂木と隅木には当初と認められる材が残されている。
上重の軒は下重と同じく二軒の繁垂木で、丸桁の組手真々寸法一一・一四尺に二五支を配し、一支寸法は四・四五六寸で、下重の一支寸法三・八二二五寸より約一・七割程広くなっている。下重より上重の支割寸法を大きくする多宝塔の例は少ないようである。なお垂木の寸法は上下重とも同寸である。
上重の垂木の割付が何を基に決められているか明確ではないが、今仮に上重柱の正背面或いは両側面中央間の柱真を直線で引き通し、その相対する二面の柱真の差し渡しの距離(平柱間)を計算すると、塔身の直径六・四九尺に対して平柱間は六・二七尺となり、これがちょうど上重の垂木支割一四支に当たっており、上重軒廻り計画の一端が想像できる。
配付け垂木は地軒が五本、飛檐軒が論治垂木を含め四本となっており、垂木の歩みは、丸桁部分も地軒と飛檐軒の配付け部分も同寸に計画していると見られ、規矩的には整っているが、軒廻り材のうち木負と茅負及び飛檐隅木は後補材となっており、多少後補の手の加わっていることも考えられる。
現状では丸桁には丸桁はね木が入っているが、修理前の実測図には丸桁はね木は描かれておらず、当初はなかったものと推定できる。
腰組の組物は上重の柱に合わせて配し、亀腹の上に直接肘木を置いて三つ斗を載せ、縁桁を受けており、大斗はない。縁桁には、簀の子縁に見せかけて縁木口型を彫りだした縁先板を載せ、縁板は布張りとし、縁上に高欄を据えている。高欄の斗束は腰組組物に合わせて割り付ける。高欄地覆の上端は緩い山形に造られ、古式な蒲鉾形が硬化変形したものとなっている。また地覆の下端は斗束部分を猫足形に残して、それ以外は水抜き状に少し繰り取られている。縁の出は一・二五尺で、直径は八・九九尺となっている。
この組物も見せかけだけのもので、実際は外部に肘木形を造り出した角材と、巻斗と面戸と縁桁を造り出した角材の二材が積み重ねられ、その上に縁先板が載せられている。またこの腰組材は、上重柱に井桁に通された腰貫の先端に納まっている。
亀腹部分は漆喰塗りとなっているが、下地は厚板から亀腹曲線を造り出した幅広の縦板材で、当初材とみられるが、これは金剛三昧院多宝塔と同様の工法である。亀腹部分の直径は一一・四尺ほどで、上重の丸桁位置となっている。この亀腹は高さが二尺ほどしかなく、小さくてやや貧弱な印象は否めない。
下重内部の天井は、四天柱内を側廻りより一段高くした、二重折上げ小組格天井である。床は拭い板敷きで、幅広の板を梁間方向に張る。
須弥壇は禅宗様式のもので、狭間の部分には左右対称な牡丹唐草文様の薄肉彫り彫刻をはめ込む。須弥壇の足元の四隅には猫足がつく。須弥壇上の高欄親柱は唐戸面を取った角柱で、柱頭に逆蓮を飾る。高欄の斗束は握り蓮で、地覆、平桁、束とも角はしゃくり面となっている。地覆と平桁の間には繰り型を切り抜いた飾り板を入れ、蝙蝠狭間風に飾っている。正面側の高欄は平桁を略し、矩形断面の架木が曲線を描いて地覆に接し、反転して先端は唐草彫刻となる。地覆と架木の間には網目文と巴文を透かし彫りに彫り出した非常に繊細な彫刻をはめ込んでいる。須弥壇は全体が黒漆塗りで、面は朱漆、彫刻部分は緑青、牡丹の花弁は朱、高欄の巴文は金に彩られ、極めて華麗なものとなっている。
この須弥壇の幅は四天柱間寸法より少し小さく、寸法的な関連性が希薄で、或いは後補のものかとの疑念も持たれるが、当初と見られる柱や床には現在の須弥壇以外の取り付き痕跡は見られず、やはり当初のものと見るべきであろう。
下重内部は、須弥壇背後の来迎壁が黒漆塗りであるのと、天井の支輪と小組の裏板が胡粉塗りである以外は彩色の痕跡はなく全くの白木であり、少し物足りなさが残る。
外部は現状では殆ど白木の状態であるが、所々に赤色の顔料が残っており、当初は丹塗りであったことが分かる。本堂も内部は白木であるが外部に丹塗りの痕跡があり、また大門にも丹塗りの痕跡があり伽藍全体が同一の意匠であった。
小屋組材はすべて昭和の取替材で古材は残されておらず、当初の状況は明らかでない。ただ、野地は上下重とも屋垂みがなく、母屋の上に直接厚板を流し板状に張り詰め、その上に瓦を葺く、かなり特異な野地の工法であり、或いは何らかの根拠に基づいたものであるかも知れないが、今確認はできない。
屋根は本瓦葺で、隅棟には稚児棟が付かない。瓦は各時代のものが混在しており、鎌倉期と認められるものも用いられている。上重の鬼瓦は特に古式な遺品として貴重である。 以上、長保寺多宝塔について歴史と各部の構造技法を述べたが、この塔は組物を大きな材から造り出しにするなど技法的に見るべきものがあり、塔全体としての姿も破条なく納められ、工匠の技術的水準の高さを示している。また蟇股や須弥壇の彫刻は洗練されており、時代を代表するものと言えよう。伽藍全体としても、ほぼ同時期の門、本堂、塔が揃って残り、中世伽藍の好例となっている。多宝塔は正平十二年(一三五七)の建立が明らかであり、その造形的な美しさや技法的な卓越さを見ても南北朝期を代表する建築と位置づけることができよう。
註
1 「下津町史」史料編・上 下津町史編集委員会編 一九七四年
p256〜263 所収
2 同書 p266〜268 所収
3 同書 p211〜213 所収
4 同書 p210 所収
5 同書 p257 「長保寺記録抜書」の中に収められている。
ただし和歌山県立博物館紀要第三号の「長保寺の伽藍に関する二,三の考察」(竹中康彦)によると、長保寺に現存している「不断念仏式」にはこの書付けはみられない という。
6 心柱銘による。この銘文は近年確認された。
歌山県立博物館紀要第三号「長保寺の伽藍に関する二,三の考察」竹中康彦 一九九八年 所収
7 心柱銘に「…諸人因下壇遷築所奉修造之也…」とあって、伽藍が移転されたことは事実と認められる。
8 長保寺にある「紀州藩霊殿」には棟札が現存しており、これによると霊殿は寛文七年(一六六七)に紀州藩初代徳川頼宣によって建立された「仏殿」であり、そのときの導師は天台に属する「雲蓋院権僧正大和尚位憲海」であって、この時天台に改めれれたと思われる。また「長保寺記録抜書」の中に
とあって、長保寺はそれまで、高野山の善集院の末寺であったと思われる。
紀州藩霊殿の棟札は次の通り(「下津町史」所収)。
9 「下津町史」史料編・上p263(2)紀州徳川家関係文書所収
10 これと全く同じ収まりの例として和歌山県伊都郡高野町所在の国宝金剛峯寺不動堂(鎌倉後期)があり、当時としては一般的な収まりであったと推定される。
11 外部の縦幣軸は腰長押と付き突けに取り合っているが、この縦幣軸をみると、現在の腰長押位置より約十センチ下に、かつて腰長押と取り合っていたと推定できる当たり痕跡と止め釘痕跡があり、内法長押を一段下げるのに伴って、幣軸はその分足元で切り縮められたと判断できる。
参考文献
「日本佛塔の形式、構造と比例に関する研究」 濱島正士 昭和五八年
「国宝 長保寺本堂修理報告書」 昭和四七年
「下津町史」 下津町史編集委員会編 一九七四年
特別展図録「長保寺の文化財−仏画と経典−」 和歌山県立博物館 平成四年
和歌山県立博物館紀要 第三号 一九九八年