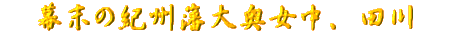老女 田川
(南紀徳川史 第7巻 P.574)
田川は幕府旗本の士、牛奥銀大夫の女。江戸市ヶ谷仲の町に生まれ、名を「ふみ」と称す。
牛奥の祖先は一条信濃守頼宗と称し武田信玄の妹聟にて信玄に仕え8万石を領し信州小松の城主たり。信玄24将の一人なり。嫡子一条六郎忠光、信州牛奥郷において高1万貫余を領す依而氏とす。忠光戦死、2男靱負頭昌重また戦死、5男織部佐昌次、牛奥村にて高1万7千石を領す。勝頼敗滅の後、天正13年酉正月13日、神君へ召しだされ知行300石を賜り大番たり。爾来世々相仕え、大番、新番、小十人等勤務。禄亦200石乃至200俵に至る。始祖頼宗より銀大夫に至て11世という。
年14初て我が内庭に仕え、名を「かつ」と賜う。後、田川に改む。名を「かつ」と賜いしに付いて一奇談ありとそは其父御番士たりし時、組の頭某に妾あり「かつ」と称し頗る悪女にして殆ど其家を乱さんとす。某之を知るも手を下す能わず。銀大夫思うに、頭は主君に等しきもの其難に迫るを傍観なしがたし。吾之を除くべしと窺うに、某にも謀り遂にかつ女を打果し、而して之を神に祭れり。然るに暫くして妻懐妊出生したるが即ちふみ女なれば、其祟りありなんとは兼ねて思いつつあるに、今又拝領の名の「かつ」なる事、名詮自證実に不可思議の因縁なりと田川自ら常に語れりという。
顕龍公、憲章公、昭徳公より今公(茂承公)に至る四公に奉仕。表使若年寄を経、老女に累進せり。性硬直豁達、男子の風あり。能く論孟の書を解し、又多芸多能にして記憶よく、事に処して鑑念根気、人のよく及ぶ処にあらず。唯己が意に飽くまでも之を貫かんとするの癖ありて、毫も他の説を容れず。自らも、
「吾は蛇の性にてねじけもの也」
と称せし程にて中々もて餘し、婀娜柔嫩を旨とせる女性輩、迷惑の事どもも少なからざりしと。然れども、人に接するに甚だ深切にして淳々後進の者を引立、御奉公の身は勤の暇には女禮、香華、手跡、折り形、結びもの、何に限らず心得あるべき事とて教え導き、私財をも擲ちて其資を助けたり。
又寡欲淡泊にして奢侈を好まず。一とせ若山にて節倹の令出て、奥向一統麁服すべしとありし時、並勝れたる麁服をなし、夏は細美布の帷子を着し(老女の身として細美を服せしは前代未聞なり)ければ皆々打驚き、余りの事とおし止むれとも中々聞き入れず。維新前後は世上甚だ物騒しく人心恟々たれば、時の世評風聞等常に心にとめて見聞し、御簾中様御守護の覚悟などさまざまと指揮し、今にも事あらんする振廻にて、かかる折は女なるらも夜毎内園を打廻り御前辺の非常を警しむべしと自から先立ちければ、さらぬだに怯気つよき少嬢等、物すごき深夜に其の恐ろしさ堪えかたきも、老女の指図詮方なく従い廻りしと。其度量おさおさ男子も及ばざる事あり。一二を左にかかぐ。
一 御簾中様初て若山へ御移住之時、君上には御上京之際いよいよ攘夷の勅諚出、若山近海通航之外国船と見れば直ちに砲撃すべしとの督促厳敷。今にも戦争起こらん気色にて、市在動揺一方ならず。執政初め有司等協議、いざと申さん時は御簾中様を川上辺へ御動座こそ然らんと、其由御廣敷御用人渡辺儀平次より上申なさんとせしに、田川承り
「そはあきれ果たる御評議かな、君上御留守中に御簾中様が此和歌山城を御明けあそばされるがよろしきものに候哉。若し強てとの儀に候はば、某御自害を御すすめ申し上げるより外なし」
と、直に覚悟の躰なるにぞ、儀平次返す辞なく議遂に止みたりとなり。
一 慶応4年辰年正月8日、大阪の敗兵和歌山へ乱入。御老若衆、初には和歌山城を根拠として御本末御人数をもって盛返さんと評議にて、今にも和歌山にて合戦も有るべきよう沙汰し、市中動揺甚しく、家財を近在へ運び、御城内も大混雑。就ては万一事ある節は、御簾中様御披き場所は野上辺かいずれへ御立退あそばされるやと御廣敷御用人初め評議区々にて御家老へも談ずれども兎や角と一決しがたき処、老女田川まかり出
「あなた方は何を左様に御心配御相談なされ候哉」
と申に付その次第を答えしに田川申候は
「上に御苦心あそばされ候はば御簾中様にも倶に御苦心あそばされ候方と存じ候。上を其儘にて御簾中様のみ御披き安閑とあそばされ候はもっての外の事。万々一かなわぬ節は私共恐れながら宜しく御守護申上る心得に付、御披き場所には及び申しまじく、御城御守りあそばされるが然るべき候」
と申切たる故、一同顔を見合わせ、評議はそのまま止みたりと。(北村長之右衛門御廣敷御用人密語)
一 明治2年正月18日老女田川、思し召しなされありたる候に付、養生長屋にて慎べく罷りある旨仰せ付けらるる候とて、誠に神妙に畏り、さて其筋之役人共、警護乗物にて養生長屋へ護送し慎所へ入れ候処、田川申候は
「このまま入り候はば宜しきや」
と申に付、「よろしく」と答えに
「さ候はば各様にはそれにて御役相済、御引取なされ候や」
と申し候ゆえ「其通の事」と申すに
「私はヶ様のものを持居候。」
とて懐中より守り刀を取り出し
「咎人は御法も御座候ならん。とくと御改めなさるべき儀にはこれ無きか。」
と、渡し候に付、いづれも打驚き赤面して受取候なり。
一 右、養生長屋へ護送するや直ちに同人部屋へ役人立越し捜索。手廻り物等一切取り上げ、政府にて逐一改めしに、一通の書類もなく、証となすべきもの更に見あたらず。唯、蜜柑山買入の書類のみありしには、津田執政も舌を巻きしと。この蜜柑山は長保寺顕龍院様御香華料に寄付奉る爲なりしと。(顕龍院様には格別に御高恩蒙り奉れりと、常に語りしとなり。以上吉田冬扇筆記。冬扇この頃奥御右筆組頭たり。)
一 幽閉中、飲料にふとあやしと感ぜし事ありて、直さま手拭にて拭い取り、用意ありし拝領の消毒剤を服し何事もなかりしが、是平素信仰念持佛の加護にてありと、手拭の拭えるところは赤黒に色変りありしを後に長保寺に示せしとなん。また、この時懐中の紅筆を濡し不浄紙に事のよし略記し女中方も油断あるまじき様にと、手寄りを求め密に奥向へ申通せしとぞ。
按ずるに、田川の罪を得しは適説なしと雖も、それこの津田又太郎へ御国政改革の御委任。同人の挙動頗る専横に似、世評紛々。故に女心に全く公家の不利を謀ると疑い、密に手筋をもって京師伏見宮に通し、又太郎を除かん事を企しやと疑われ、ここに及びしならんと云。この時、田宮儀右衛門(御廣敷御用人)も何か預りしにや、同時に厳譴を蒙りたり。
一 其の後、程なく東京宿元へ御戻しとなり、奥詰半隊長南条和田右衛門、陸路護送。市ヶ谷なる牛奥左金吾方へ引渡したり。道中いたって謹慎慇懃にして、南条の身から斯と聞て後は何程すすむるとも決して先たち入浴をなさず。山坂には付添の者へ多少の心付をなし、神社仏閣あればそれぞれ寄付を依頼するをもって、「かかる身になられし上は後々の嗜みこそ肝要なれ必ず心遣いしたまうな」と、南条止むれども多分に賜りものしたれとて受引かざりしよし。
一 東京へ帰着後は御家父様方初御忌日には上野真如院等へ参拝怠らず。明治5年の冬は御簾中様にも東京へ御移住、女中も御共にて移り御代拝先にては折々落合たれば、御殿へも参られよとしばしば進め慰めしより、いとやつやつしき風情に草履はき雨傘肩に背負いなどして、仲の口まで至り時々の野菜もの等携え来り音信しけるゆえ、奥へ上り給えとすすむれば
「私は咎人に候」
と、大声にいいはなちなかなか承引せず。明治7年11月14日、御簾中様御逝去あそばされしと承りおよび、御同所様には御年11にて京都より御下向の砌御共いたし、爾来永々仕え奉り、御親しみも一方ならず思召されけるに、かく成り果てたまうとて物狂うばかりに打歎き千々に心をくるしめども、御ゆるしなき内は上り候事もならず。せめては御葬送には陰ながら御共仕らんものと前夜中より御邸門の外にたたずみ夜を明し、御出棺の後より忍びかくれに御共し、御一七日の内昼は御廟所番人の目に障りなんと御廟近き池上村見知りの方へ身をひそめ居て、夜に至れば本門寺の山へ登り、松杉凄寥たる御廟墓の側に独り通夜し奉る事、七夜の間怠りなし。かくとは更に知る人もなかりしか。ふと御廟番の前川某心付きて後に分りし由。これらの事いつしか御聴に達しいたく不憫に思召され、その後御ゆるしの御沙汰ありければ深く有り難がり、打晴て伺公しつるに昔にかわらず元気よく、さりとて前々の事など露ほども口に出さず、只々面白き戯れ言語り出、更に頓着もなかりしとぞ。
一 明治13年5月の此齢73の老躯をいとわず跌然独歩、乞食老婆の姿にやつし菅笠竹杖わらじがけ百十有餘里、永の旅路の艱苦を忍び、紀伊国海士郡浜中村長保寺へたどり着き、堯海阿闍梨に便り寺中なる最勝院の一室に止住し(籍は浜中村、船木善之進方へ移す)御先塋の御墓守りを吾任として、毎月御歴世様方初め御忌日毎御廟の塵を掃い花を供し香を手向け、参拝奉仕の躰御在世に仕え奉る如くにて、いかなる厳冬酷暑の暁も烈風暴雨の夕べも一日怠らず、7ヶ年の間終始一の如くなりし。この御廟墓は山上山下、場広き所々に散在し階段の昇降のみにても壮年輩なお容易からぬに、女性しかも極老の身、実に誠忠無二の精神にぞ恐ろしけれと人皆感じあえり。而して日毎山に入りて薪を拾い谷を渡りて水を汲み、自ら炊しき自ら食し、仏を礼し經を誦し、余暇あれば喫茶詠歌をたのしみ唯風月を友として、偶人に接するも風流のみ談じ絶て世事にわたらざりけり。
一 明治14年10月12日、堯海阿闍梨を請し戒師となし落髪染衣、妙鏡と改む。生前自ら葬地を卜し、青き自然石に田川墓と彩りたる少碑を建て我が隠居所也と折々打ち廻りたのしみが、同19年5月初旬微恙に罹り就褥。僅に同22日安然として帰寂す。時に齢79歳慶徳山中予定の墓に葬る。法名浄光院水月妙鏡禅尼と号す。
田川、なかんずく香の道に堪能。また好んで女禮式の事を調査し、或いは紐の結び方、紋切り形の事など熱心緻密に調べ、その雛形及び書類、存するもの挙て数うべからず。常に筆硯を事とし古事記全部(楷書仮名付き)、女禮式書、香道の書、歌書、その他見聞の巷説風評にいたるまで手書するところはなはだ多く今現存せり。
死に至るの前日、はや明日と期すれば、永々師恩の辱きを謝し兼て暇乞をもなさんと人のおし止むるをも肯せず、病をつとめ杖にすがりて方丈に至りければ、堯海阿闍梨いたく驚き、もっての外と扶けかかえて漸く帰臥せしめたりと。死に臨みてなお屈せざるかくのごとし。実に稀世の烈婦なりしと堯海師語りたり。